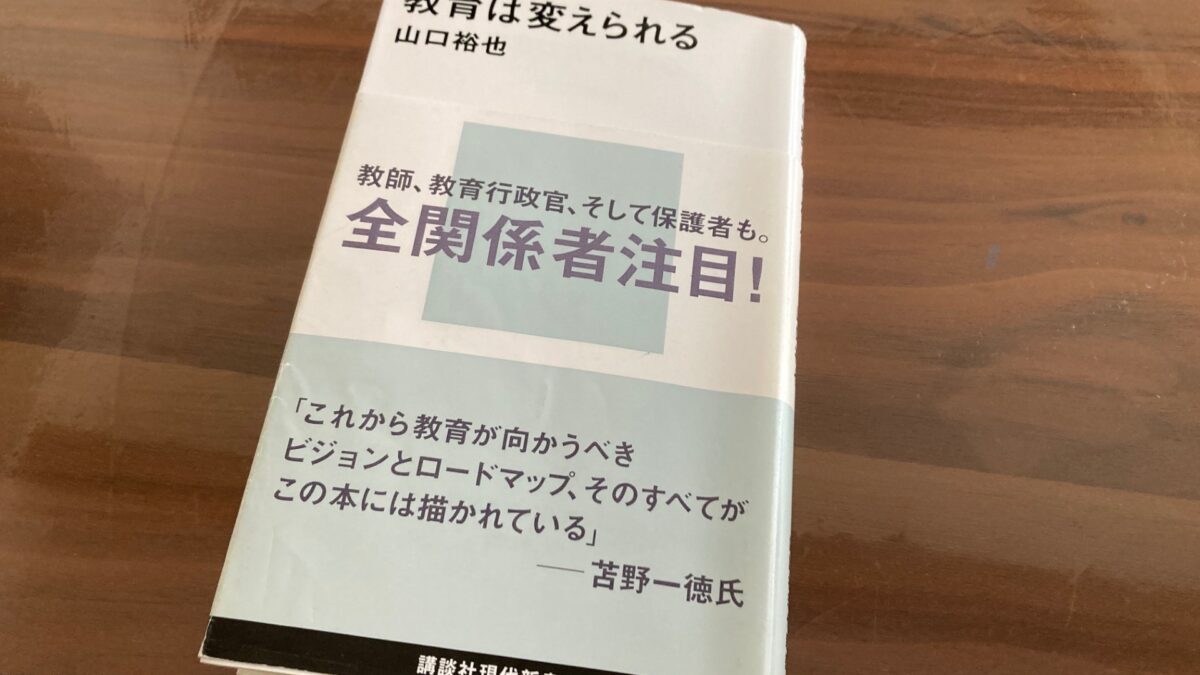まなびしごとLABの風間です。
こんにちは!
今回、ご紹介する本は、山口裕也さん著の『教育は変えられる』です。
私は教育×まちづくりを大きな軸に活動しているので、最近は教育の歴史についても非常に興味があります。
こちらの本では公教育の成り立ちやその意義について学ぶことができ、これからの公教育について考えるヒントが満載でした。
先日の読書会でも紹介させていただいたので、改めて本書で特に気になった部分をまとメモしていきます。
ゆる読書会「好奇心が刺激される本」(in マナビバ!本屋ときがわ町)を開催しました(2025年7月20日) – まなびしごとLAB
まとメモ
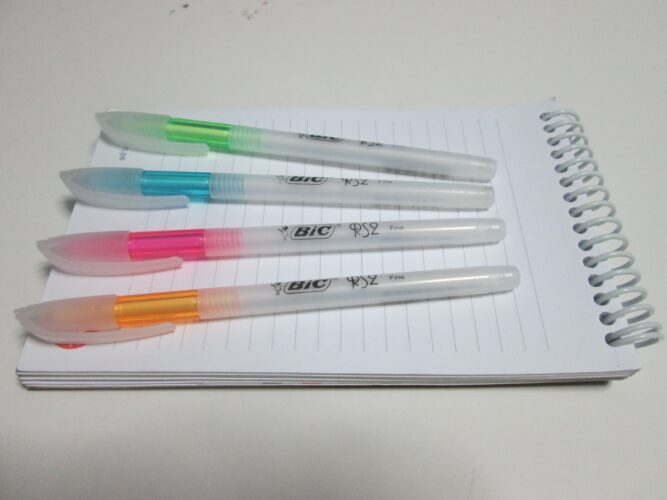
はじめに 教育は変えられる
・世界には、自分とは異質で多様な「人・物・事」が存在します。人はそのような「人・物・事」との出会いから、さまざまな「段差」につまずくことになるのです。そう、学びとは、この「段差」を乗り越えるために必要な「資質」や「能力」を獲得することで、人に成長を促すための営みなのです。そして、「成長」とは、何よりもまず、学びを通して資質や能力を獲得し、「わたしが生きたいように生きる」自由を拡大していくことなのです
第一章 自分の物語を生きるための学び 「一斉・一律」から〈多様性と一貫性〉へ
・「これからの学びを考えるうえで、一番大切なことは何か」と問われたら、どのように答えるでしょうか。私ならこう答えます。それは「自分で選ぶ」ことである、と。より的確には、「共に生きる」中で、自ら選び決める経験を積み重ねること
⇒ アントレプレナーシップ教育の一番大きな意義はここにあると思う。
・学びは、「自立」とともに「共生」のための営みでもあり、この両者の上に立ったところに「よりよい」成長が実現するのです。「自立」とは、あくまでも、「共生」をその底に敷いた「社会的自立」でなくてはなりません。多様で異質な人々が豊かに折り合う世界を実現するためには、誰もが人として対等であることを認め合い、たがいの自由を尊重し合うという意味においての「相互承認」の感度を育むことが不可欠
・学制は、「みな同じ」をいわば「目標=終着点」に定めたという意味において日本史上の画期となりました
・「自分」で「選ぶ」。自分で選び「決める」からこそ、「もっと・より以上」を求めて「探究」に「浸る」。その中でこそ、「共に生きる」「生かし合う」という「協同」がおのずと生まれてくる。その自然な遊び=学びを、「みな違う」を考え方の始発点にして、小学校、さらに中学校へとつなげ・・・自由と相互の承認に溢れた、すべての子どもにとってよりよい成長の機会とする。これからの学びの在り方を考える出発点は、ここにあります。すなわちこれが、「公教育の構造転換」を実現するための最初の土台となる考え方です
・特色として容認するためには、条件があります。その中核になるのは、「自校・自地域に特有の課題を捉える」「各種調査結果を踏まえる」「学校の棚卸(杉並流スクラップアンドビルド)を前提に」です。・・・地域社会の状況を含め、子どもたちの過去ー現在ー未来を考え続けることが要請される
・教育という舟を浮かべる豊饒な海、学校から地域へと拡がる「社会」にこそ〈協働〉の本質がある
第二章 生かし合う人材と組織 「依存と孤立」から〈協働〉へ
・協同も、基本は学習者が自ら選び取る学び方の選択肢の一つとして位置づけます。その目的は、「真」の「主体性」と「多様包摂性」を育むこと、分かりやすく言えば、「自由」を支える「自ら行動を起こす意志」と、「相互承認」を支える「多様で異質な他者と共に生きる意志」を育て上げることにあります
・学びの構造転換の考え方を、現行制度の延長線上でもっともラディカルに追究するならどうなるでしょう。私なら、学習指導要領の総則に規定された「社会に開かれた教育課程」の未来の姿として、教育課程が「個別化」し、現在のそれが「学校としての協同に関する全体計画」へと位置づけを変える姿を見ます。そのとき、個別化して一人一人のものとなった教育課程は、その編成権を、学習者・保護者・校長の「三社合意」に移行する
・「生きたいように生きる」自由の内実は、一人一人で異なっています。だからこそ、教育課程は、学校と保護者のみならず、学習者自身を含めた三者の合意によって編成されるとき初めて、子どもたちを真の人生の主体とする学びの支えになるのです。そしてこれこそが、公教育のよさをはかる規準としての「普遍福祉」、つまり、「すべての人のよりよい生」にかなう在り方なのです
・教員の役割も、おのずと定めることができます。学習者が自分で選び決めながら進める学びに後追いで関わるという基本姿勢のもと、「A学びたいこと」「B教えたいこと・学んでほしいこと」「C学ばなければならないこと」の関係において、一人一人にA∩B∩Cを目指しつつ、ひいてはAにBとCが包摂される地点を目指すこと
・総括評価としての評定の在り方も、その主たる機会と材料を一斉に行うワークテストや定期考査のみにの求めるのではなく、一人一人が自らの探究計画に位置付ける、いわば「力試し」の総括となっていくでしょう。つまり、学習評価の個別化・多様化です
・子どもたちにとって、生きる可能性の源泉となるものは何でしょうか。言うまでもなく、自己肯定感です。自分の選択や決定を、本当に尊重し応援してくれる人たち。それゆえ交換や代替のきかない、心底大切だと思える人たち。そうした人たちとの関わりの中で、自分という存在が個性を失うことなく、社会に包まれているという実感。このような自己肯定感があってこそ、子どもたちは、よりよい成長という自分の可能性を信じ、自らの選択と決定を貫くことができる
・学び成長するのは、何も子どもたちだけではないということです。教員のみならず、保護者や地域等学校関係者をはじめとした大人は、子どもたちの「学びの支え手」「教育の担い手」であると同時に、生涯にわたる「学び手」でもあります。さらに言えば、子どもと大人の別なく、全ての人は「社会のつくり手」です
・支援本部員となる方々にとって学校に関わることは、学びの機会でもあり、学校を通してみなと共に社会をつくる機会でもあります。その実感や悦びがもてない限り、地域の協力を得たどんな教育活動も、例えば「金の切れ目=縁の切れ目=事の尽き目」となって持続可能な仕組みにはなりません
第三章 求めに応える施設・設備 「定型・無味」から〈応答性〉へ
・体と知の力差がこれまでのような経済的不自由をもたらさなくなったとき、道徳の感度がよりいっそう重視される時代が来る・・・人間と機械の境界が曖昧になる時代だからこそ、欲望・願望が生む問いや、身体がもたらす温もり、後述する美的感覚といった「人間らしさ」がより大切になる
・学び方とは、資質・能力の三つの柱を活用し、一人一人異なった人生において、「必要なときに、必要なことを、自ら学び身につけることのできる」力を意味します。そしてまた、人生におけるどんな未知の事象・現象との出会いからでも、「自分なりに問いや課題を立て、自分たちなりの方法で知を学び取る」自律的・協同的で探究的な学び方こそ、これから子どもたちに育むべき資質・能力の本質であり総体だということです
・今、学校の内で起きていることは、20年後や30年後に学校の外で起きることにつながります。学校教育に関することは、それがどのような話題であれ、「内」と「外」を一対で、かつ、「過去ー現在ー未来」という時間軸の中で捉えなければならないということです
・「自分たちのことは自分たちで決める」こと。その始まりは、すでに第一章で述べた「自分で選ぶ」ことにあります。つまり、自治とは、「みな違う」を考え方の始発点とし、一人一人が自分で選ぶことから始まり、自分たちのことは自分たちで決めることにその内実があるということです
・都市が、人の温もりや美を失って定型・無味にとどまるのは、「オーナーシップ」という意味での自治とその積み重ねを欠くからです。「自分たちのもの」という実感がなければ、大切にしない
⇒ 不満や文句があれば行政に言う。誰かがやってくれるだろうと「他人事」のまちになってしまっている。「自分たちごとのまち」にしていくには、自治の精神が必要。それには教育の役割が大きい。
・公教育としての出発点は、やはり学校建築にあります。子どもたちが、いずれある未来を選び取るための原体験となるように、教室と降車を学習者・生活者主体のプロジェクト材とする。自分たちの「らしさ」や「得意」、「お気に入り」や「大好き」で環境を彩りながら、徳や美の感度を共に鍛え合っていく。・・・真に学習者・生活者主体を追究し教育課程が個別化する未来の学校施設は、都市を学習材・プロジェクト材とした「探究の基地」に転換するということ
⇒ 「学校」という空間に限定する必要はないと思う。学校の拡張として地域を捉え、地域全体を学びのフィールド=探究の基地(ラボ)と考えることができるのではないか?
・都市とは、そして、学校とは、近代合理性や経済合理性を乗り越えた先にある未知の、学びと成長にとって価値ある偶然の出逢いをもたらす場であってほしいと思います
第四章 引き受け合う行財政 「無責任」から〈支援と共治〉へ
・子どもたちの多様性は、公立学校の魅力を考えるうえで欠かせない要素です。各学年二学級を何とか維持する程度にまで小規模化したA校では、それがすっかり失われていました。しかも、教員は、こうした状況下では「みな同じ」を強化する傾向があります。人数が少なくなると、教員主体の授業が行いやすくなるからです
⇒ 少人数ほど個別化しやすくなると思っていた。実際はどうか?データはあるか?
・集合的効力感を育むためには、どうすればよいでしょうか。それは、自己効力感が自分で選び決めたことをやり遂げたときに高まるように、自分たちで選び決めたことを達成する経験を積み重ねることです。・・・何より問わなければならないのは、集合的効力感を育む自己選択・自己決定を基礎とした「集合的決定」・・・「自分で選ぶ」ことから始まって「自分たちで決める」ことに至る自治の経験を十分に積み重ねているかどうかです
⇒ 「自分で決める」「自分たちで決める」ことを通じて、自治がつくられる
・自治は、市民社会の意思決定、つまり「政治」の本質です。市民社会における政治は、多くの人にとって投票行動を通した代表選出というやり方での関わりになることから「誰かに委ねる」ものと誤解されていますが、考え方の本質は、自分たちで「引き受ける」ことにあります
・自分で選ぶ経験を、共に生きる中で積み重ねていくからこそ、自分たちのことを自分たちで決め、引き受け合うことができるようになっていく
第五章 自分達の物語を紡ぐための公教育 「外在」から〈内在〉へ
・「共に生きる」中で「自分で選ぶ」経験を積み重ねていくことにより、「自分たちで決める」、本当に自分たちにしか解決できない問題を「引き受け支え合う」ことができるようになっていく。この学びと成長の道筋は、言い換えれば、「自分の物語を生きるための学び」から始まって「自分たちの物語を紡ぐための公教育」に至る
メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています

毎月はじめに、メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています。
前月に取り組んだ各プロジェクトの状況、一般社団法人ときがわ社中の活動、地域でのしごとづくりに役立つ本のご紹介、今後の予定などをまとめています。
サンプルや登録フォームはこちらのページからご覧いただけます。
地域でのしごとづくりに取り組んでいる皆さまのお力になれたら嬉しいです!