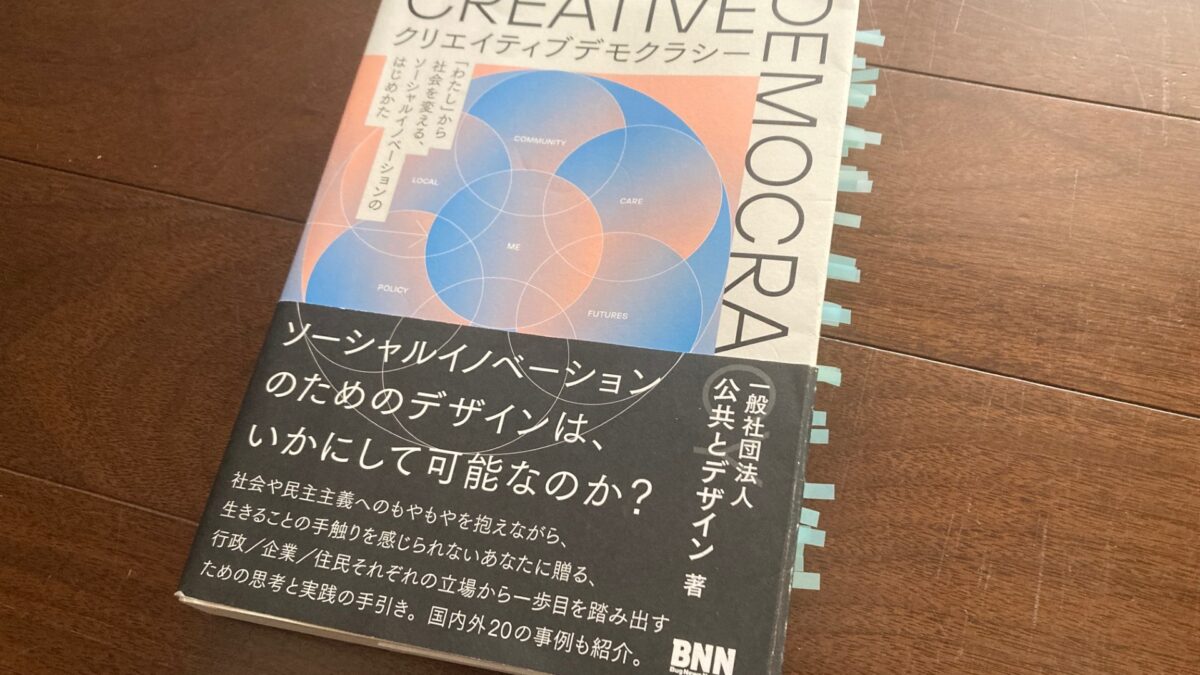まなびしごとLABの風間です。
こんにちは!
今回、ご紹介する本は、一般社団法人 公共とデザイン様著の『クリエイティブデモクラシー 「わたし」から社会を変える、ソーシャルイノベーションのはじめかた』です。
主タイトルよりも副題に惹かれて購入しました。
結論からいうと、めちゃくちゃおもしろかったです!
何がそんなにおもしろかったかというと、私が地域で取り組んでいる中で考えていたことと非常に似ていて、自分のしごとの内容や取り組み方を、もう少し視野を広げて考えることができるのではないかと気づいたことと、それを伝えるための言葉の使い方の新たな発想が得られたという2つの理由があります。
以下、本書で特に気になった部分をまとメモしていきます。
まとメモ
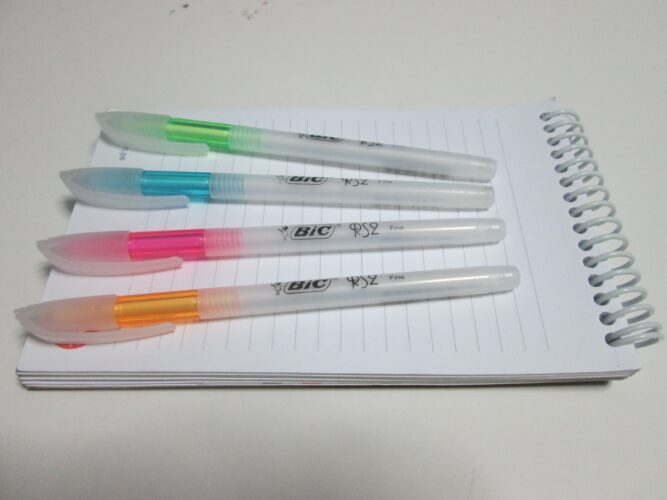
1-1 デモクラシーの危機とはわたしの危機でもある
・投票率が低いこと、政治への無関心、これが問題ではない。民主主義におけるわたしたちの手応えの感じられなさ、実践により社会を変えていけるという機会が足りないことが問題である。無関心はその結果である
・「これは自分がやることで影響を与えられる」「社会は変えられる」そういった経験と実感を得られる環境でなければ、「わたしがわたしを生きる」ことは困難
⇒ 日本財団が実施している18歳意識調査で、日本人は「自分の行動で国や社会を変えられると思う」と回答した割合が6か国(日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド)中最下位。選挙の投票率も低い。同じ問題を抱えているのではないか
・民主的なプロセス・環境において、人々の「社会は変えられる」という経験と実践をもたらすことで、人々は自らが買えられるんだという実感を持ち、初めて自らの手で社会をつくっていけるという「よき市民」になっていく
1-2 わたしの生き方と民主主義
・制度によってわたしたちがつくられるだけではなく、わたしたちの実践や行動が表出したものが制度や社会をとりまく習慣になっていく、という流れもつくることができる
1-3 クリエイティブデモクラシーとは何か:民主主義と創造性
・クリエイティブデモクラシーとは、一人ひとりの創造性を信頼し、それぞれの内発的な創造性から生まれるプロジェクトによって形成される民主主義のかたちです。それは当然個人からも生まれうるし、地域の共同体からも生まれうる。
・ただ「やっていいよ」と言われるだけでは何もできません。…義務的な民主主義の捉え方をしているうちに、わたしのこうしたいが失われつつある現代。そのためには、異なる他者との交わり合いが重要です。
・多くの場合の創造的活動は、「気づいたらやっていた」「動き出さずにいられなかった」という衝動にもとづくものではないでしょうか。能動的に、あるいは論理的に「自分のやりたいこと」を考えてもむずかしい。
⇒ 探究学習においても、やりたいことを考えるより、好きなこと、楽しいと感じることのような感情の側面から進めた方がいいかもしれない
・出逢いによって「こういう生き方もあったのか」「こんな自分もありえたかもしれない」といったところから、自分の「こうしたい」を発酵させてつくりあげていくことが、クリエイティブデモクラシーを実現する環境として必要です。
1-4 クリエイティブデモクラシーとは何か:活動・実験としての民主主義
・「わたくしたちが探求を進めていくなかで獲得する知識は、誤りを完全に免れた意見ではなく、その可能性をいつも内包した信念である」というように、そもそも完全な正しさなど存在しないというスタンスが、学びや実験の反復につながっていきます。
・複雑な社会に向き合ううえで、合理主義的なアプローチも重要ですが、それだけでは限界が来てしまいます。社会の組織や個人全体を、実験があちらこちらで生まれるような創造的な状態にしていくことが重要です。
⇒ 安斎勇樹さん「冒険的な世界観」
・私的な関心を共有し合い、実際に行動したことで人々の賛同を呼び、結果として公的な関心につながっていく。正解に向かって一直線で生まれる取り組みには限界があります。実験を起こりやすくする環境を整え、生まれた活動を必要に応じて支援する。
⇒ どうしたら「実験を起こりやすくする環境」をつくれるか?
・自分の欲望、こうありたい・こうしたいを実験でき、社会をつくっていけること。一人ひとりが「わたしはどう生きたいのか」と生き方を問い直し、自分なりに答えを出していくこと。・・・誰もが社会に対するデザイン実践者なのです。だからこそ、各々がバラバラで実験を繰り返す社会環境が必要です。
2-1ソーシャルイノベーションとは何か
・「厄介な問題」には客観的な正しさの基準はないため、こうした自らの軸にもとづく判断が求められます。一人称の「わたし」から始まることが、ソーシャルイノベーションの大前提なのです。
・いくつかの定義が存在しますが、共通して主張される特徴は、あらゆる人やものごとが関わり合い、新たなやり方で新たな価値を社会にもたらすこと。これがソーシャルイノベーションの大きな像です。
・多様なセクター・人々が手を取ることで生まれる「新たな価値」とは、何かしらが変化した結果です。イノベーションは「革新」とよく訳されますが、差異や変化の結果、価値が生じます。
・それぞれのレイヤーで少しずつ変化が生まれ、それが別のレイヤーの変化とも結びつき、大きな変容につながっていく。・・・ソーシャルイノベーションによる社会変容は、究極的にはわたしたちがコントロールできるものなのではないでしょうか。
デザインとソーシャルイノベーション:社会のリデザインに向けて
・共創は異なる知が混じり合うことだけでなくて、これまで声をもちえていなかったり、表現をしきれていなかった人々、格差によって力をもちえていなかった人々、その関係性が書き換わり、互いに学び合い、変わっていくーーこの地平が共創の本義です。
・「現実は今とは違っててもいいんだ、違う可能性がありうるんだ」と変革可能な実感を持てる状況をつくり。それが、これからのイノベーションのポイントです。
2-3 本書におけるソーシャルイノベーションの再定義
・「各々のローカルで生きる状況の当事者=わたしと多様な他者が新しい関係性を育みながら、これまでの当たり前を問い直し、システムの変容を促す創造的活動」
→ ソーシャルイノベーションの4つの特徴
①オルタナティブなあり方と変容性
②誰もが主体となる
③ローカルで起こる
④社会関係を再生する
・変容とは、ビフォー/アフターといったある境界で区切られる前後のようにはっきりとは分けられません。目に見えないなかで、何かしらの変容が常に生成されています。
・ソーシャル・コモンズも関係財も、直接的に形成することはできません。それらは結果的に生まれるものであり、「互いにこのくらいの信頼関係になるように」といった目的設定を行えばそこに向かわせることができるわけではない。
2-4 「わたしたち」から始まるソーシャルイノベーション
・ソーシャルイノベーションは、いかにして始まるのか。それは常に、衝動に突き動かされた創造的な人々から生み出されます。
・ライフプロジェクトは一人の衝動から始まり、他者と共に既存のルールを疑いながら異なる可能性を投げかけることで、新たな世界を立ち上げる営みです。この「プロジェクト」という言葉にこそ、ソーシャルイノベーションやデザインのコアが織り込まれています。
・プロジェクトはpro-jectであり、前方へまだ見ぬ世界へ投げ出す・投企する、といった意味をもちます。
⇒ プロジェクトの概念は探究に通じる
・何らかの活動やプロジェクトを立ち上げてすぐに「これはイノベーションだ」という定義はできません。そのためには、長く続けて育てていくことが必要です。・・・実践活動の過程そのものに私的な意味を見出せなければ決して続きません。ソーシャルイノベーションは、常に「わたし」や少数の「わたしたち」のライフプロジェクトがその原始にある。そのためには、「わたし」と「他者」の交わり合いが重要である。
・「異なる可能性の想像」と「内省・表現の繰り返し」から切り離せない営みが、対話です。むしろ、対話こそが最も中心にあると言えます。
・生きること自体が、常に周りの人々、出来事、ものごととの対話から成り立って、わたしたちは常に変わり続けている。発展途上である、未完である。どんどん新しい自分になれる。
・他者と共につくることは、必ずしも誰もが同じゴールに向かう必要性を意味しません。しかし、「他者の表現に接触する時には、そこに現れる環世界の構造が自分の世界認識に染み込んでくる」とドミニク・チェンさんが述べるように、他者との会話や表現の交わし合いが環世界を拡げ、それによってこれまでに想像しえなかった可能性が浮かび上がります。
・地域内での出逢いの機会創出はソーシャルイノベーションへの条件のひとつになります。
・すでに地域にネットワークやタッチポイントを持っている組織が、率先して自身の役割を再定義し、出逢いを生み出し、社会関係をつなぎ直すきっかけづくりをすることも、ソーシャルイノベーションのエコシステムには必要です。
2-5 ソーシャルイノベーションの発展過程
・創造的なコミュニティは、開放的で出入りも自由、関わり方も自由、加えて先に述べた多様な他者が共存できる、といった点が特徴的です。同質性による閉じたコミュニティではなく、異質性にもとづく開かれたコミュニティです。
・誰もが自分なりの参加方法を見つけられることで、多様な協働がコミュニティ内で生まれます。
メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています

毎月はじめに、メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています。
前月に取り組んだ各プロジェクトの状況、一般社団法人ときがわ社中の活動、地域でのしごとづくりに役立つ本のご紹介、今後の予定などをまとめています。
サンプルや登録フォームはこちらのページからご覧いただけます。
地域でのしごとづくりに取り組んでいる皆さまのお力になれたら嬉しいです!