まなびしごとLABの風間です。
こんにちはー!
スキマ時間を使って、これまで考えてきたことを少しずつ言語化することに取り組んでいます。
今回は「探キュベーション」フィールドとしての地域の可能性について考えてみたいと思います。
「探キュベーション」という言葉は耳慣れないかと思いますが、もちろん私の造語で、最近、ハマっている「探究」に、「イノベーション」と「インキュベーション」をかけ合わせた言葉です。
「探キュベーション」フィールドとしての地域について考える前に、まず、これらの言葉の意味を簡単に整理しておきます。
探究とは?
「探究」とは、自分で問いを立て、考え、そのときそのときの自分なりの「答え」を探し続ける学びの姿勢だと考えています。
ちなみに、私が高校で一緒に取り組んでいる探究プログラムでは、「自己探究」「社会探究」「自分と社会の関わり方の探究」という大きな3つのステップによって構成しています。
イノベーションとは?
「イノベーション」とは、一般的に新しい価値を生み出りたり、既存の枠を超えた変化を起こすことを意味します。
必ずしも技術だけでなく、仕組みやサービス、社会のあり方にもあてはまります。
インキュベーションとは?
「インキュベーション」とは、もともとは英語で「孵化(ふか)」を意味する言葉ですが、ビジネスでは起業および事業の創出をサポートするサービス・活動を意味する言葉として使われます。
「探キュベーション」のフィールドとしての地域

次に、「探キュベーション」のフィールドとしての地域について考えていきたいと思います。
私は「地域でしごと」をつくることを主な生業にしていますが、公務員を辞めて地域で活動するようになると、地域にあるさまざまな可能性を活動する前よりももっと感じるようになりました。
もちろん「課題」と言われることもたくさんあるのですが、逆にいえば手がつけられていない課題はチャンスともとらえることができます。
一方で、地域には「どうせ何もない」「誰も動かない」というあきらめの声を聞くことも残念ながら多くあります。
だからこそ、私は、地域を探究(問いを見つけ、自分なりの「答え」を探し続ける場)、イノベーション(新しいことが生まれる場)、インキュベーション(育む場)として、とても豊かなフィールドになりえるのではないかと考えています。
それを表現したのが「探キュベーション」という言葉です。
では、地域をフィールドとした探究、イノベーション、インキュベーションにはどのような可能性があるかを考えていきます。
地域×探究

まずは地域と探究との関わりを見ていきます。
高校の先生や生徒さんたちだけでなく、地域の方と話をすると、地域には暮らしの中で感じるちょっとした違和感や「もっとこうだったらいいのに」という想いが、実はたくさん眠っています。
これらはすべて、探究の入り口になります。
単に「あったらいいな」「こうなったらいいな」ではなく、「自分ができることは何だろう?」「どうしたらもっと楽しくなるだろう?」とジブンゴトの行動につなげていくかが重要だと考えています。
「社会」というと、大きな世界を想像しがちですが、社会はもっとずっと近くにあります。
地域とは学校の外に広がるまちであり、家のすぐ近くのまちであり、自分にとっての身近な「社会」で、地域に出ることは社会に出るファーストステップになります。
つまり、地域は、自分という枠を少しだけ広げた半径5メートルの社会ともいえます。
地域という自分にとって身近な社会で、小さな挑戦ができる。
だからこそ、私は、地域は探究に最適なフィールドなのではないかと考えています。
地域×イノベーション

次に地域とイノベーションの関わりについて考えていきます。
探究を続け、ジブンゴトとしての問いを重ねていくうちに、小さなチャレンジが生まれてくることもあるかと思います。
これまでそうしたチャレンジが起こらなかったからこそ、地域にはさまざまな課題がくすぶっていました。
そのため小さなチャレンジが生まれてくること自体が、地域にとってのイノベーションだといってもいいとのではないかと思います。
イノベーションというと、どうしても大きな革命的な出来事をイメージしてしまうかと思うのですが、必ずしも難しいものである必要はありません。
たとえば「日常を少し良くする行動を起こす」「人と人を新しくつなぐ」ことも、小さなイノベーションになります。
地域には、小さくても新しいチャレンジや新しい出来事、新しい組み合わせ、新しい視点が必要なのです。
また、地域でこそ、そうした小さな出来事が大きな変化を生むきっかけになるかもしれないという期待もあります。
しかも、身近であるため、自分がやったことの変化が見えやすく、手応えも感じやすいといったこともあります。
そのため私は、地域はイノベーションが生まれやすいフィールドでもあると考えています。
地域×インキュベーション
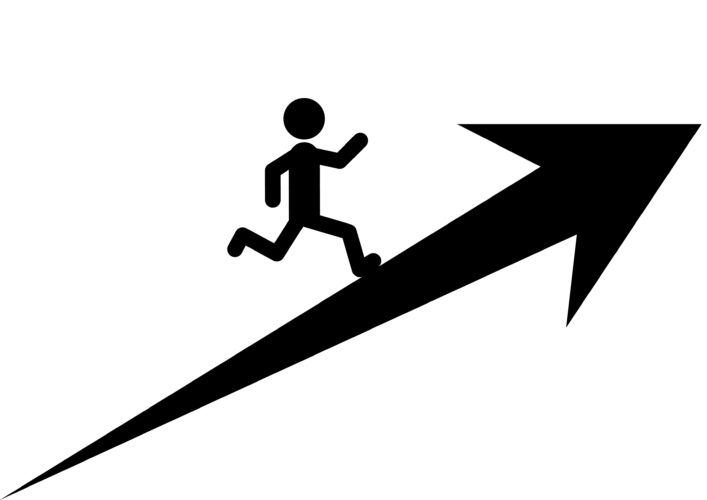
最後に地域とインキュベーションの関わりについて見ていきます。
もちろん地域の特性によっても違いますが、地域には、挑戦を受け止め、ゆっくり育てる土壌があります。
むしろ都市部のように大きく急な変化が歓迎されない側面もあるかと思います。
そのため、大きな成功を急がなくていいというのが一種の利点です。
むやみに大きくするのではなく、長く続けることを重視するのが地域での活動のポイントではないかと私は考えています。
また、地域はさまざまな面で人手不足を抱えています。
そういう意味では人がすごく大事にされる場所です。
もちろん、人の成長も大事にされます。
さらに、そのようにして人が育てば、地域も一緒に育っていきます。
情緒的な言葉を使うなら、大都市のようなスピード感より、「一緒に育てよう」という温かさが地域の魅力だと思います。
そのため、これまで見てきたような探究や小さなイノベーションをいかに大事に見守り、育てられるかが、これからの地域にとってはますます重要になると私は考えます。
それがチャレンジの孵化器、インキュベーションのフィールドとしての地域の可能性です。
まとめ
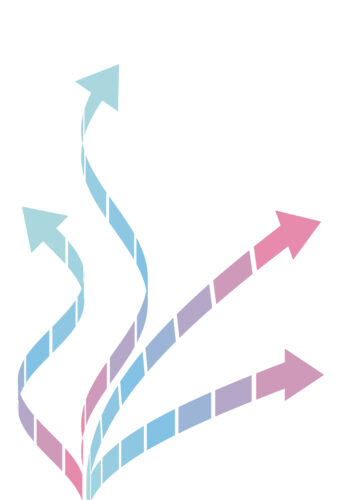
以上、見てきたように、地域は自分にとって、ジブンゴトの問いや答えを探すきっかけとなる身近な社会の入口であり、すぐに手が届くチャレンジできる場所でもあります。
地域で小さく挑戦し、自分を試し、時には失敗することで、社会が身近にあることや、自分にも動かすことができるんだという小さな実感を得ることができます。
このようにして地域は、「探究」「イノベーション」「インキュベーション」が生まれやすく、人も地域も一緒に育つフィールドになりえるのではないかと考えるようになりました。
私が提案する「探キュベーション」は、
①自分で問い・答えを探し続ける(探究)
②小さくても新しい価値を生み出す(イノベーション)
③周りに支えられながら、ゆっくり育つ・育てていく(インキュベーション)
この3つが、地域という身近な社会で、自然に循環する考え方です。
そして、そこに挑戦する人が、自分自身の成長を感じられること。
そしてそうした人たちの活動によって、地域が変わっていくこと。
それが、「探キュベーション」の本当の価値だと思っています。
ただ、それ自体が目的というわけではなく、どんなものかはわからないけど、それぞれの人が行動したり、または仲間と共創したりすることによって、少しずつ地域が変わり、人が成長し、良い方向に変わっていくプロセスそのものを指すものとして考えています。
最後は抽象的なお話になってしまいましたが、思いついたばかりのことなので、高校での探究学習や地域での活動を通じて、今後も探究を続けていきたいと思います。
メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています

毎月はじめに、メルマガ「月刊 地域でしごとをつくるマガジン」を発行しています。
前月に取り組んだ各プロジェクトの状況、一般社団法人ときがわ社中の活動、地域でのしごとづくりに役立つ本のご紹介、今後の予定などをまとめています。
サンプルや登録フォームはこちらのページからご覧いただけます。
地域でのしごとづくりに取り組んでいる皆さまのお力になれたら嬉しいです!

